こんにちは!ここ最近は今まで読みためた本の感想も放出中です。
ニュージーランド生活でのまとめをこのブログに書き出すのですが、2年ほどためたので毎日忙しいです笑
コツコツやるのが大事ですね。
今回はニュージーランド滞在中、日々の暮らしの中で少しずつ読んでいた村上春樹の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』。
Kindleで買って、夜の読書時間に毎晩じっくりと読み進めていきました。
村上作品はこれまでにも、『ノルウェイの森』『ねじまき鳥クロニクル』『騎士団長殺し』『1973年のピンボール』『1Q84』などを読んできましたが、この作品はその中でも特に”脳みそ”にくる一冊でした。
まぁタイトルからしてわけわからないですもんね。
それで上下巻あって分厚いとなるとなかなか物好きしか読まないのかも、、、笑
現実と幻想、ふたつの世界を旅する物語
あらすじについては多く語りませんが、この物語はふたつの世界が交互に進んでいく構成です。
-
一つは、情報処理を生業とする”計算士”が主人公の現実世界――ハードボイルド・ワンダーランド。
-
もう一つは、壁に囲まれた街で”影”と別れて暮らす男の幻想世界――世界の終り。
まったく違う物語が、交互に描かれ、やがて静かに重なっていきます。
印象的だったシーンとキャラクターたち
まず驚いたのは、老博士の研究内容。
**「これが1985年に書かれた小説なのか?」**と思うほど、現代のAIや意識研究を先取りしたようなテクノロジー描写があってびっくりしました。
そして、物語終盤。影との別れ方が想像以上にあっけなくて、
「え?まじで、そこで終わる?」
と軽く放心しました。笑
最後にボブ・ディランの『風に吹かれて』が流れるシーンも印象的で、その後何度も聴き返しましたし、ギターの練習もしましたよ笑
それから、ヤミクロという謎の生き物が東京の地下鉄と融合してる世界観も、個人的には親しみがありました。自分も大学時代にさんざん使っていた地下鉄が、こんな風に物語とリンクしてくるのかと妙にリアルでした。
あとは最後の日比谷公園でのシーンも、昔の僕を思い出しましたね。
この本がくれた問い
読んでいて一番考えさせられたのは、**「記憶とは何か?」**ということ。
人の思いや記憶、無意識の世界がどうなっているのか。物語全体の崩壊感や曖昧さに、逆に心地よさを感じる部分もありました。
あと、ところどころに登場する芸術作品や音楽、文学の引用も、読み物としての幅をぐっと広げてくれていて、読書中ずっと飽きませんでした。
共感したところ:丁寧な日常から生まれる冒険
この作品の主人公って、基本的には淡々と日常を過ごしているようでいて、いつの間にかとんでもない冒険に巻き込まれていくんですよね。
それがなんだか、自分自身の暮らし方とも重なるなと感じました。
特別なことをしなくても、日々を丁寧に送っていれば、いつの間にか自分の意図していない面白いところに辿り着いている――そんな感覚です。
読後の余韻とおすすめポイント
読了後の感想は、正直なところ
「え?これで終わり?」
という感じ。
解決されていないことがたくさんあるのに、でもなぜか納得させられてしまう。不思議と心が癒やされるような、不完全な読後感でした。
この本は、**「夜に静かに読むものが欲しい人」**におすすめです。
意味があるようでないような世界観に、ふっと入り込んで、気づいたら夢の中。
よく眠れます(笑)
まとめ
村上春樹の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は、情報社会を生きる現代人にこそ刺さる、静かで深い読書体験をくれる作品です。
「自分の内側にこんな世界があるのかもしれない」と思いながら、ページをめくってみてください。




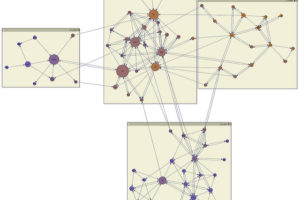

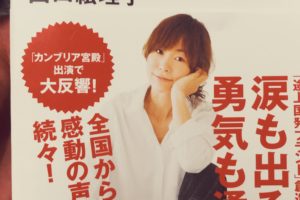

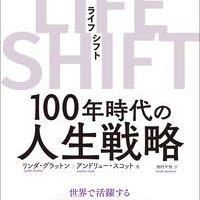
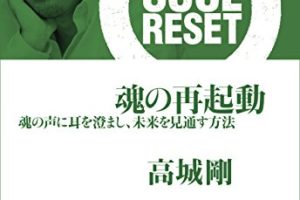



コメントを残す